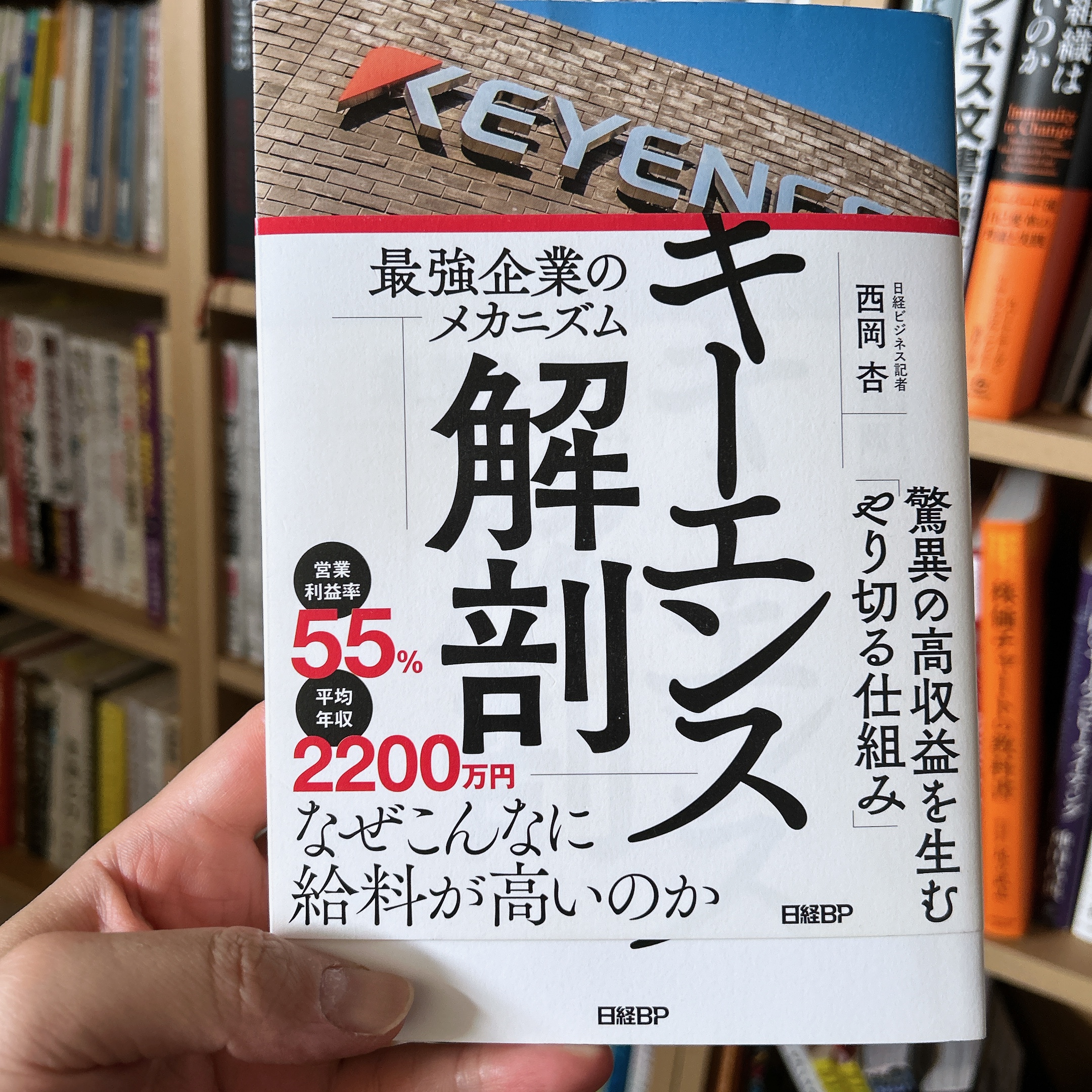「キーエンス解剖」
手に取った理由:
- ブックオフで安かったからwただでさえ顧客優先主義で薄利で苦しんでいる企業が多い中、どうやって営利55%を達成しているのか。
読了後の課題に対する解決策、考え方等
- 想像を超える提案をする
29ページ
先回りして本質を探り当てて解決することで、大きな価値を提供できる。顧客も気づかない潜在需要こそ、キーエンスにとっては宝の山なのだ。それは、米アップルの創業者であるスティーブ・ジョブズ氏が「人は形にして見せてもらうまで自分は何が欲しいか分からない」と喝破したのと通じる。 - 商談のレベルを引き上げる「ロープレ」1000本ノック
40ページ
18時になると1日を締めくくる恒例行事、「ロープレ」が始まる。10分~15分、毎日繰り返すのがキーエンス流。歯を磨くように当たり前にやる。直接見せ、デモをする。キーエンスは顧客の前でどれだけデモを見せたのかの回数もKPI(最重要業績評価指数)として記録している。 - 「ニーズの裏のニーズ」を探れ
71ページ
例えば、顧客がタブレットを探している。便利で使い勝手が良い、画面の大きさはこのぐらいなど、これは表のニーズである。裏のニーズは「なぜこれが必要なのか」「これを導入してどんな成果を望んでいるのか」を顧客に問うことで導き出される。タブレットを導入して営業効率を高めたい、月に10日ほど出張するセールス担当者が迅速に情報を共有しやすい環境を作りたい、などという裏のニーズがわかればタブレットだけでなく、情報共有に適したソフトウエアなどを提案し、顧客の課題を解決するために一歩踏み込んだ提案書ができる。一般的な営業は、タブレットが欲しいという普通のニーズまでしか取れてないことが多い。 キーエンスでは入社半年で、「ここまで聞いてきてください」と教えられる。 - ヒットを生む「ニーズカード」
75ページ
ひとりが月に1件以上提出するとされる「ニーズカード」。世の中にあるものでは、まだこれができないというニーズを書き込むもの。「今はげんこつサイズの商品を、数センチメートル角くらいに小型化したい」といった具合に、顧客からのヒアリングをもとに書き込む。 - 原価の削除よりも付加価値を高める
91ページ
原価も頑張るが、基本的には付加価値を上げることに重点を置いている。顧客の作業時間をどれだけ短縮できるか、工数をどれだけ減らせるかなどの価値を伸ばすのが先決である。顧客が欲しいと思うものを作っていてはすでに遅く付加価値は上がらない。顧客のニーズの裏にあるニーズに応える商品を考え続ける。付加価値の創造こそがキーエンスの存在意義で、「商品を通じて世の中のありようを変えたい」という思いを持ち、全社のベクトルがそろっているのがキーエンスの強みである。 - 社員の時間も大事な資本「時間チャージ」
135ページ
前の年度に生み出した付加価値を、全社員の労働時間で割った数が新年度が始まるとキーエンス全社で共有される。時間チャージとは、社員一人が平均で1時間にいくらの粗利を生んだのかを示す数字だ。キーエンスの社員は、1時間で生み出すべき粗利を念頭に置きながら日々の仕事に取り組んでいる。「出ていくお金をすごく意識して切り詰めようとする会社はたくさんある。もちろんそれも大事だが、まさに今過ごしているこの時間も大切な資本だ。」無駄に時間を垂れ流していては、経営理念にある「最小の資本で、最大の付加価値」が実現できないと意識させる狙いである。この考え方が社員に定着しているのは、社員が自分を律する意識を強く持っていることもあるだろうが、給与の決め方とも無縁ではなく、業績賞与が連動する形になっているため、努力しても報われないと思ってしまい、社員の意識が徐々に緩んでいくということはない。 - いろいろなものを強引にでも
「数値化」する文化
143ページ
販売促進の企画書一つとっても、出展の費用対効果や何人の顧客の名刺を集めるか、営業フォローをどのぐらいしてどれだけの売上高に繋げるかといったことを書き込むルールがあった。ぼんやりとしたところを残さず、具体的に計画し、それをもとに議論する。そうした仕事術が全社的に浸透している。
感想
数値化、1時間当たりの粗利を計算する時間チャージという考え方は、面白いですよ。中小企業の経営改革なんかこれだけでよい。ただし、みんながついてこられるかというかいかにこの考え方を浸透させられるか。社員からしたら仕事をさせられるわけなので、自己成長や愛社精神などは鍵となる。2023年4月13日 13:20
一覧へ